食事介助や口腔ケアは、
- 利用者さんの状態によって適切な方法がわからない
- 上手くいかない時の対処法がわからない
など、ケアに不安を感じることも多いでしょう。
介護の現場での食事介助や口腔ケアの目的は
- 利用者の方が楽しく食事できること
- 誤嚥性肺炎のリスクを下げるため
今回ご紹介する内容は
- 食事介助と口腔ケアの基本
- 利用者の状態に合わせたやり方
- トラブルへの対処法
ぜひ、最後までご覧いただき参考にしてください。
食事介助の基本|誤嚥を防ぎ、楽しく食べるための3ステップ
食事介助は、利用者さんの安全と快適さが最優先。
3ステップを意識しながら、誤嚥のリスクを減らし楽しく食事ができるようにしましょう。
| ステップ | |
|---|---|
| 1: 環境を整える | テーブルや椅子の高さを利用者さんに合わせて調整。 安定した姿勢で食べられるよう環境を最適化することが大切。 |
| 2: 食べやすくする工夫 | 嚥下機能に合わせて ・一口量を少なめ ・ペースト状にする などの工夫を。 食形態を見直すことは誤嚥のリスクを最小限に抑えられます。 |
| 3: 食べ終わったら口腔ケア | 食後は口腔内を清掃し清潔を保ちます。 適切な口腔ケアを行うことで誤嚥性肺炎のリスクを下げることができます。 |

介助者も座って食べさせるなど、できるだけ目線を合わせて行いましょう。
誤嚥を防ぐにはあごを引くことが大切!
あごと鎖骨の間は指4本分を目安にするといいですよ。
ステップ1:環境を整える
食事介助の第一歩は、利用者が安全に食事を楽しめる環境を整えること。
身体機能に合わせた適切な姿勢で座ることが大切なポイントになります。
ベッド上であれば30度~60度にギャッジアップ。
車いすの場合は背もたれに寄りかかるなどの工夫をします。
テレビを消すなど食事に集中できる静かな空間を確保する工夫も大切です。
食事環境を整える際のチェックポイント
- 適切な座位姿勢になっているか
- テーブル周りに物がなく、食事に集中できる環境か
- 照明や温度、音楽など、五感に配慮されているか
食べる行為に専念できるリラックスした雰囲気が大切です。
ステップ2:食べやすくする工夫
食事形態は主に流動食→ソフト食→刻み食→常食(普通食)となります。
| 流動食 | 重湯(お粥の上澄み)や具なしの汁物のような水分摂取を目的とした形態 |
| ソフト食 | ミキサーなどで砕きペースト状にしたもの |
| 刻み食 | おかずを包丁などで刻んだもの(みじん切り、半刻みなど咀嚼・嚥下状態に合わせる) |
飲み込むときむせにくくするために、トロミをつけることもあります。

ちなみに、おかゆにも段階があり
重湯→三分粥→半粥→七分粥→全粥
と少しづつ水分が少なくなります。
ステップ3:食べ終わったら口腔ケア
食事介助の最後に欠かせないのが口腔ケアです。
口腔ケアには、
- 歯磨き
- 舌磨き
- 義歯の手入れ
などが含まれます。
利用者の状態に合わせて、優しく丁寧に行うことが大切です。
口腔ケアの主な効果
- 口腔内の清潔を保ち、むし歯や歯周病、誤嚥性肺炎などを予防
- 味覚の向上
- 口臭の予防

口腔ケアと合わせて、「口腔体操」や「唾液腺マッサージ」もおすすめです。
口腔ケアの重要性|誤嚥性肺炎予防や全身の健康維持に
口腔ケアは、高齢者の健康維持に欠かせない大切な役割を担っています。
適切な口腔ケアを行うことで、誤嚥性肺炎のリスクを下げることができます。
誤嚥性肺炎とは、唾液や食べ物が気管に入り込んでしまうことで引き起こされる肺炎のことです。
口腔内の細菌が原因で発症するため、口腔ケアで口腔内の細菌を減らすことが予防につながります。
さらに、口腔ケアは全身の健康維持にも重要な役割を果たします。
口腔ケアがもたらす3つの効果
口腔ケアには、大きく分けて以下の3つの効果があります。
- むし歯や歯周病の予防
歯や歯茎を清潔に保つことで、口腔内の細菌の減少、むし歯や歯周病の発症リスクを下げる - 誤嚥性肺炎の予防
口腔内の細菌が気管に入り込むのを防ぐことで、誤嚥性肺炎のリスクを軽減 - 認知症予防や全身の健康維持
口腔ケアを続けることで、脳の活性化や全身の健康状態の維持に繋がる
このように、口腔ケアは単に口腔内の衛生を保つだけでなく全身の健康にも大きな影響を与えます。
口腔ケアの頻度とタイミング
口腔ケアは、1日に複数回行うことが大切です。
理想的なタイミングは以下の通り。
- 朝食前: 夜間に溜まった口腔内の汚れを除去
- 食後: 食べ残しを取り除き、細菌の繁殖を防ぐ
- 就寝前: 夜間の口腔内環境を清潔に保つ
つまり、朝・昼・夕の食事前後に行うのが理想的です。
経口摂取がない場合は、1日2~3回のペースで行います。

寝る前の口腔ケアは不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)の予防にもつながります。
実践編|状態に合わせた食事介助と口腔ケア
利用者さん一人ひとりの身体状況や認知症の有無、嗜好などによって食事介助や口腔ケアの方法は異なります。
適切な介助を行うには、個別対応が不可欠です。
【要介護度別】食事介助のポイント
- 自立: 食事の準備や後片付けを手伝う
- 要支援: 盛り付けや食べにくい部分を切る
- 要介護1: 介助者が見守りながら促す
- 要介護2以上: 一口ずつ口に運ぶ
要介護度が低い方は、自立支援を意識しながら食事の準備や盛り付けを手伝うことがポイントです。
中程度の要介護度の方は、安全面に十分注意を払いながら
- 食事動作の介助
- 姿勢の保持
- むせ防止
などを行うとよいでしょう。
重度の要介護度の方は、全面的な食事介助が求められます。

食事介助のときのスプーンの使い方を説明している動画もご紹介します
【ケース別】口腔ケアの方法
まずは口腔内の観察から始めましょう。
- 歯の状態
- 粘膜の状態
- 舌の動き
- 唾液の量
などを確認し、 それに応じたケア方法を選びます。
- 自力で口腔ケアができる場合: 歯ブラシ、舌ブラシを使用し、自身で行う
- 一部介助が必要な場合: スポンジブラシなどを使い、介助する
- 全介助が必要な場合: 吸引器を使用しながら、口腔内を清潔に保つ
また、唾液分泌を促進するためレモン水の提供や口腔体操も有効です。
優しく丁寧に、利用者の状態に合わせた口腔ケアを心がけましょう。
- 認知症: 声かけを丁寧に行い、拒否時は無理強いしない
- 摂食・嚥下障害: 姿勢に注意し、むせ込まないよう細心の注意を払う
- 口腔内の痛み: 優しく清潔に保つ
状態に合わせた適切な食事介助と口腔ケアを行うことで、利用者さんの QOL 向上に繋がります。
全介助、寝たきりの方の口腔ケアのやり方を説明している記事も参考にして下さい。
困ったときの対処法|よくあるトラブルと解決策
●食事中にむせてしまった場合は、すぐに食事を中断し安全な姿勢を確保します。
頭を前に軽く傾け、タッピングなどの刺激を与えましょう。
●口を開けてくれない利用者さんとは、まず信頼関係を築くことが大切です。
ゆっくりと話しかけ、無理強いせずに気持ちに寄り添いましょう。
口腔ケアを嫌がる方には、方法を工夫すると上手くいくこともあります。
- お気に入りの歌を歌いながらケアする
- 本人が好きな味の歯磨き粉を使う
- 鏡を見せながら一緒に行う
など、一人ひとりに合わせた対応が重要です。
食事中にむせてしまう
食事中にむせてしまうのは、高齢による嚥下機能の低下が主な原因です。
加齢とともに嚥下反射が衰えると食べ物が喉に詰まりやすくなります。
むせが続くと、
- 呼吸困難になる
- 食事が入りにくくなり体重減少につながる
- 誤嚥性肺炎のリスクが高まる
このような影響が出る可能性があります。

むせの原因は、年齢とともに食道入り口を覆う筋肉の動きが鈍くなるため。
この筋肉が上手く動かず、食べ物が気管に入ってしまうのです。
食形態の工夫や姿勢を整えるなど、誤嚥を防ぐ対策が重要になります。
利用者さんの状態に合わせた食事介助が何より大切です。
口を開けてくれない・口腔ケアを嫌がる
食事介助や口腔ケアの際に口を開けてくれない場合、まずは利用者の気持ちに寄り添うことが大切です。
不安や恐怖心から拒否反応が出ている可能性があります。
穏やかな声かけと、ケアの必要性を分かりやすく説明することで徐々に理解を深めてもらいましょう。

病気が原因の開口障害だったり
認知症などで開口拒否の場合もあります。
口をあけてくれない利用者さんへのやり方の参考になる動画の紹介です。
利用者一人ひとりの心理状態に合わせた対応が何より重要です。
焦らず、じっくりと信頼関係を築いていくことがポイント。
要因を探る
口腔ケアを嫌がる利用者さんへの対応は、要因を探ることが大切です。
- 過去の経験から口腔ケアを恐れている可能性
- 痛み・違和感がある
かもしれません。
まずは無理強いせず。
それでも極端に拒否が続く場合は、口腔内の異常や認知症の進行が考えられます。
医療機関に相談し、適切な対応をとることが重要になります。
ポイント
- 嫌がる理由を探る
- 無理強いせず、できる範囲でケア
- 拒否が続く場合は、医療機関に相談
食事介助と口腔ケアを学ぶ|スキルアップのための情報
食事介助と口腔ケアのスキルアップには様々な学習機会を活用することが重要です。
専門書籍から実践的な動画まで、自分に合った方法を見つけましょう。
おすすめの書籍
食事介助と口腔ケアを学ぶ上でおすすめの一冊が
「『食べる』介護がまるごとわかる本」です。
この本では、食事介助の具体的な困りごとの解決策から、正しい口腔ケアの方法まで、食事に関する介護の知識が網羅されています。
また、「基礎から学ぶ口腔ケア 改訂第3版」は、口腔ケアの基礎知識から実践的な技術まで体系的に解説された定番の教科書です。
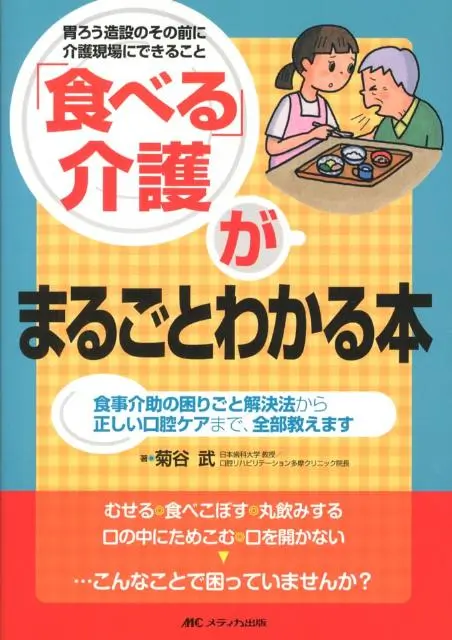

どちらの書籍も介護現場で活躍する専門家による実践的な情報が満載で、食事介助と口腔ケアのスキルアップに最適な一冊となっています。
役立つサイト・動画
食事介助と口腔ケアの基本を動画で学べるサイトが多数あります。
「ケアーズサポート株式会社」のチャンネルでは、2分で学べる介護動画が公開されており、食事介助の流れや注意点が簡潔に解説されています。
さらに、「ミッレケア・アカデミー」のサイトでは、現役看護師が監修した記事が掲載されており、利用者の状態に合わせた食事介助方法や口腔ケアのポイントが詳しく学べます。
介護施設での研修
介護施設では、利用者さんの安全と生活の質(QOL)を高めるため、食事介助や口腔ケアに関する実践的な研修が行われています。
●食事介助
- 利用者の状態に合わせた食事形態の選択
- 誤嚥を防ぐための介助方法
- 楽しく食事ができる環境づくり
●口腔ケア
- 口腔内の清潔保持による誤嚥性肺炎予防
- 義歯の手入れ方法
- 拒否があった場合の対応
実技指導を受けられるほか、他の介護職との情報交換の場にもなります。
まとめ|食事介助と口腔ケアで、利用者のQOL向上を目指そう
食事介助と口腔ケアは、要介護者さんの健康維持と生活の質(QOL)向上に欠かせない重要な支援です。
適切な食事介助と口腔ケアを行うことで、以下の効果が期待できます。
- 誤嚥性肺炎の予防
- 全身の健康維持
- 食事の楽しみを取り戻す
利用者さん一人ひとりの状態に合わせた、適切な食事介助と口腔ケアを心がけることが重要です。
これらのケアを適切に実践することで、誤嚥や感染症のリスクを下げ利用者さんの健康と生活の質(QOL)の向上につながります。
在宅介護の場合、食事を楽しいものにするためや介護負担を軽減するために、
「宅配食サービスの利用」という方法もあります。
やわらか食などメニューも豊富なので、活用してみるといいでしょう。



