高齢者はさまざまな病気を抱えており、介護度も軽度~重度とたくさんのケースがあります。
そのため、いろいろな病気への対応が求められます。
- 高齢者に多い病気の症状
- ケア方法
これを理解することは、質の高いケアを提供するために不可欠です。
この記事では、
- 介護職が知っておきたい病気の基礎知識
- 感染症対策
- 医療的ケア
- コミュニケーション方法
などをご紹介します。
- 高齢者に多い病気ランキングTOP10
- 褥瘡
- 経管栄養
- 吸引などの具体的なケア方法
- 病気の伝え方や共感的なコミュニケーションの重要性
についても参考になると思います。
介護現場で役立つ!病気の基礎知識

厚生労働省が発表している「要介護状態の原因となる疾病」も参考に。
高齢者に多い病気ランキングTOP10
それぞれの病気の特徴を理解することで、より適切なケアを提供できるようになります。
ランキングは高齢者に多くみられる病気の一例であり、発症率や順位は統計データによって異なる場合があります。
あくまで参考として、個々の利用者さんの状態を正確に把握し適切なケアを行うことが重要です。
| 順位 | 病気名 | 主な症状 | 介護上の注意点 |
| 1位 | 認知症 | 記憶障害 見当識障害 判断力の低下 など種類によって症状は様々 | 安全確保 見守り 問題行動にある原因を探る 不安にさせない 刺激を与えつつ負担をかけない工夫 コミュニケーション重視 |
| 2位 | 脳血管疾患 (脳卒中) | 片麻痺 言語障害 意識障害 など 発症部位によって症状は異なる | リハビリテーションへの協力 機能訓練 嚥下機能の評価 誤嚥性肺炎予防 |
| 3位 | 心臓病 | 息切れ 胸痛 動悸 など | 安静の確保 無理のない活動 服薬管理 定期的な健康チェック |
| 4位 | 糖尿病 | 多尿 多飲 体重減少 など 合併症に注意 | 血糖値管理 食事療法 運動療法 足病変の予防とケア |
| 5位 | 高血圧 | 自覚症状は少ないことが多いが、放置すると脳卒中などの危険性が増加 | 食塩摂取制限 運動療法 服薬管理 血圧測定 |
| 6位 | 肺炎 | 咳 痰 発熱 呼吸困難 など 高齢者は重症化しやすい | 感染予防 安静の確保 呼吸管理 適切な水分補給 |
| 7位 | 骨粗鬆症 | 骨折しやすい | 転倒予防 カルシウム・ビタミンDの摂取 運動療法 |
| 8位 | 関節リウマチ | 関節の痛み 腫れ 変形 日常生活に支障をきたす場合も | 安静と運動のバランス 疼痛管理 関節保護 リハビリテーション |
| 9位 | パーキンソン病 | 震え 動作緩慢 姿勢反射障害 など | 安全確保 機能訓練 薬物療法 生活環境の調整 |
| 10位 | 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) | 咳 痰 呼吸困難 など 徐々に進行する | 呼吸リハビリテーション 禁煙指導 感染予防 酸素療法 |
感染症対策マニュアル【予防と発生時の対応】
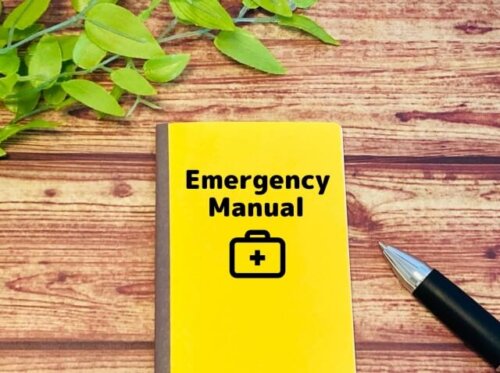
介護現場で多い感染症の種類
介護現場では様々な感染症のリスクが存在します。
高齢者は免疫力が低下しているため、感染症にかかりやすく重症化しやすい傾向にあります。
| 感染症 | 症状 | 感染経路 | 予防策 |
| インフルエンザ | 発熱 咳 鼻水 頭痛 筋肉痛 など | 飛沫感染 接触感染 | ワクチン接種 手洗い マスク着用 換気 |
| ノロウィルス胃腸炎 | 嘔吐 下痢 腹痛 発熱 など | 経口感染 糞口感染 | 手洗い 手指消毒 嘔吐物・排泄物の適切な処理 |
| 肺炎 | 咳 痰 発熱 呼吸困難 など | 飛沫感染 接触感染 | ワクチン接種 手洗い マスク着用 換気 |
| 結核 | 咳 痰 発熱 倦怠感 など | 飛沫感染 | 早期発見 治療 マスク着用 |
| MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) | 皮膚の化膿 発熱 など | 接触感染 | 手洗い 手指消毒 適切な消毒薬の使用 |
| ロタウイルス胃腸炎 | 嘔吐 下痢 腹痛 発熱 など | 経口感染 糞口感染 | 手洗い 手指消毒 嘔吐物・排泄物の適切な処理 |
高齢者施設では「感染症対策マニュアル」を作成し、施設独自の対策を立てることが重要です。
感染症の予防策
感染症の予防に重要な3つの要素です。
- 感染源の排除:患者の早期発見と隔離、適切な消毒など
- 感染経路の遮断:手洗い、手指消毒、マスク着用、適切な換気など
- 抵抗力の向上:健康管理、栄養バランス、十分な睡眠など
特に、標準予防策(スタンダードプリコーション)の実施が重要です。
- 手洗い・手指消毒の徹底
- マスクの着用
- 使い捨て手袋の使用
- 適切な換気
- 汚染された物の適切な処理
- 感染者への適切な隔離
これらの対策を徹底することで、感染症の発生リスクを大幅に低減することができます。
感染症発生時の対応手順
感染症が発生した場合、迅速かつ適切な対応が重要です。
- 早期発見:発熱、咳、下痢などの症状に注意し、早期に発見
- 隔離:感染した利用者を速やかに隔離し、他の利用者との接触を避ける
- 感染経路の特定:感染経路を特定し、感染拡大を防ぐための対策を行う
- 消毒:汚染された場所や物品を適切に消毒する
- 医療機関への連絡:必要に応じて医療機関に連絡し、適切な治療を受ける
- 保健所への届出:法定感染症の場合は、保健所に届出を行う
- 記録:発生状況、対応内容などを記録に残す
ここでも「感染症発生時の対応マニュアル」などが重要になります。
- 施設独自の対応手順を策定
- 定期的な訓練
普段から意識し、職員間の周知徹底を行うことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。
医療的ケアが必要な病気とその対応

高齢者の介護において、
- 褥瘡
- 経管栄養
- 吸引
など医療的なケアが必要となるケースは少なくありません。
介護スタッフが多い介護施設では、看護より先に介護士が異常に気づくことも日常的にあります。
褥瘡の予防とケア
褥瘡(じょくそう)とは、皮膚や皮下組織の潰瘍のこと。
特に寝たきりの高齢者に多く見られます。
長時間の圧迫や摩擦、ずり落ちなどが原因で起こり、痛みや感染症を引き起こします。
早期発見と適切なケアが重要となります。
褥瘡のステージと症状
褥瘡は、その深さや症状によってステージに分類されます。
ステージが進むにつれて治療が難しくなるため、早期発見が重要。
| ステージ | 症状 |
| ステージⅠ | 皮膚の赤み 圧迫を除去しても赤みが残る |
| ステージⅡ | 表皮や真皮の損傷 浅い潰瘍や水ぶくれ |
| ステージⅢ | 皮下組織まで達する深い潰瘍 脂肪組織が見えることもある |
| ステージⅣ | 筋肉や骨まで達する非常に深い潰瘍 壊死組織が見られる |
| 未分類 | 創傷の深さが不明な場合 壊死組織で覆われている場合 |
- 疼痛
- 発熱
- 悪臭
などの症状が現れる場合もあります。
早い段階で医師に報告し、処置することが重要です。
褥瘡のケア方法:体位変換と創傷ケア
褥瘡のケアは、予防と治療の両面から行う必要があります。
予防策としては、
- 定期的な体位変換
- 適切なスキンケア
- 栄養管理
などが挙げられます。
体位変換は2時間ごとに行うことが推奨されています。
また、床ずれ予防マットレスや体位変換器の使用は介護者の負担軽減にもつながり、効果的です。
創傷ケアは医師の指示に基づき、
- 洗浄
- 消毒
- ドレッシング材の選択
などを行います。
褥瘡の悪化を防ぎ、治癒を促進することができます。
経管栄養の基礎知識とケア
経管栄養とは、経口摂取が困難な場合に胃や小腸にチューブを通して栄養を供給する方法です。
高齢者では嚥下障害や消化器系の疾患により、経管栄養が必要となるケースが多く見られます。
経管栄養の種類と方法
経管栄養には、胃ろう、鼻胃管、経鼻経腸栄養などいくつかの種類があります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、状態や医師の指示に基づいて選択されます。
| 種類 | 説明 |
| 胃ろう | 胃に直接穴を開けてチューブを留置する方法 長期的な栄養供給に適している |
| 鼻胃管 | 鼻からチューブを胃に挿入する方法 短期的な栄養供給に適している |
| 経鼻経腸栄養 | 鼻からチューブを小腸に挿入する方法 胃の負担を軽減できる |
経管栄養のケア:栄養管理と感染予防
経管栄養のケアでは栄養管理と感染予防が特に重要です。
栄養状態を定期的に確認し、必要に応じて栄養剤の種類や量を調整します。
また、チューブの管理、清潔な手洗い、定期的なチューブ交換などにより感染を防ぎます。
吸引の基礎知識とケア
吸引とは、気道に分泌物が溜まっている場合に吸引カテーテルを用いて除去する方法です。
高齢者では、嚥下障害や呼吸器系の疾患により吸引が必要となるケースがあります。
吸引の種類と方法
吸引には、経鼻的吸引と経口的吸引、気管切開の吸引などがあります。
最近は、研修を受けた介護士が吸引を行う施設もあります。
| 種類 | 説明 |
| 経鼻的吸引 | 鼻からカテーテルを挿入して吸引 |
| 経口的吸引 | 口からカテーテルを挿入して吸引 |
| 気管切開吸引 | 気管に挿入した管に溜まった痰を清潔なカテーテルで吸引 |
吸引のケア:安全な実施と感染予防
吸引は、感染症のリスクがあるため無菌的な操作が重要です。
- 吸引前後の手洗い
- カテーテルの滅菌
- 吸引器の清掃
など感染予防対策の意識が必要です。
また、吸引による身体への負担を最小限にするため、吸引圧や吸引時間を適切に管理することも大切です。
利用者とのコミュニケーションを円滑にする方法

介護の現場では、利用者の方々との良好なコミュニケーションが質の高いケア提供に不可欠です。
特に、病気や症状を抱える利用者の方々に対しては
- 正確な情報伝達
- 共感に基づいた対応
などが求められます。
病気の伝え方:わかりやすく丁寧に説明するポイント
利用者の方々に病状を説明する際には、できるだけ専門用語を使わず、分かりやすい言葉で話すことが重要です。
「患者中心のコミュニケーション」を意識し、利用者の方々の理解度や認知機能を考慮した説明を心がけましょう。
| ポイント | 具体的な方法 |
| 専門用語を避ける | 難しい医学用語は避け、日常生活で使う言葉で説明 例:「心不全」→「心臓が弱って体がうまく働かなくなっている状態」 |
| ゆっくりと丁寧 | 早口の説明は理解が追いつかず、不安感を増幅させる ゆっくりとしたペースで、言葉を選びながら説明 |
| 図解やイラストを活用 | 病状を視覚的に理解しやすくする 説明内容の理解度を高めることができる |
| 繰り返して説明 | 一度の説明では理解できない場合もあるため、重要な点は繰り返し説明 理解度を確認しながら進める |
| 質問しやすい雰囲気を作る | 質問しやすい雰囲気を作ることで、利用者の方々の不安や疑問を解消し、信頼関係を築くことができる |
説明後には必ず理解度を確認し、必要に応じて補足説明を行うようにしましょう。
共感的なコミュニケーションの重要性
利用者の方々の気持ちに寄り添い、共感的なコミュニケーションを心がけることは、
- 信頼関係を構築
- 良好な関係を維持する
ために非常に重要です。
単に病状の説明をするだけでなく、不安や心配、感情を理解しようと努める姿勢を示すことが大切です。
| 共感的なコミュニケーション | 具体的な方法 |
| 相手の話をじっくり聴く | 話を遮らない 相手の言葉に耳を傾ける ノンバーバルコミュニケーションも意識 |
| 感情を理解しようと努める | 言葉からだけでなく、表情や仕草などからも感情を読み取る努力をする |
| 共感の言葉を伝える | 「大変でしたね」「お辛いでしょう」など、共感の言葉を適切に伝える |
| 感情を否定しない | 相手の感情を否定や軽視しない 感情を受け止め、共感する姿勢を示す |
| 信頼関係を築く | 継続的なコミュニケーションを通して、信頼関係を築く |
共感的なコミュニケーションは利用者の方々の安心感につながり、より効果的なケアを提供することに繋がります。
傾聴のスキル:利用者の気持ちを理解する
傾聴とは、単に相手の話を聞くだけでなく相手の気持ちや考えを理解しようとする積極的な姿勢です。
利用者の方々の話を真剣に聞き、共感することで信頼関係が構築され、より深い理解へと繋がります。
| 傾聴のスキル | 具体的な方法 |
| アイコンタクト | 相手の目を見て話すことで、真剣に話を聞いていることを伝える |
| 相づち | 「はい」「そうですか」「なるほど」などの相づちを適切に打つことで、話を進めやすくする |
| 要約・確認 | 相手の話を要約し、理解度を確認することで誤解を防ぐ |
| 沈黙 | 沈黙の時間も大切にする 考えを整理する時間や、感情を落ち着かせる時間として尊重 |
| 感情に共感 | 相手の言葉だけでなく、表情や態度から感情を読み取り共感する |
介護職のための医学用語集

よく使う医学用語一覧
介護現場では多くの医学用語が使用されます。
かんたんな一覧ではありますが、理解を深めることで職員間のコミュニケーションを円滑に進め、
より質の高いケアを提供できるようになります。
あ行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| アルツハイマー病 | 徐々に記憶力や認知機能が低下していく神経変性疾患 認知症の代表的な原因の一つ | 進行性で、現在のところ根本的な治療法はない |
| 意識レベル | 意識の清明度を表す指標 覚醒度、見当識、反応性などから評価される | GCSなどが用いられる |
| 嚥下障害 | 食べ物を飲み込む機能に障害がある状態 誤嚥性肺炎のリスクを高める | リハビリテーションや食事形態の工夫が必要となる |
か行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 喀痰 | 気管支や肺から排出される粘液性の分泌物 色や粘度から病状を推測できる | 色の変化や量の変化に注意が必要 |
| 関節リウマチ | 関節の炎症を伴う自己免疫疾患 痛みや腫れ、変形を引き起こす | 薬物療法やリハビリテーションが中心 |
| 冠動脈疾患 | 心臓の筋肉に酸素や栄養を供給する冠動脈の病気 狭心症や心筋梗塞を引き起こす | 生活習慣病が主な原因 |
| 狭心症 | 心臓に血液を送る冠動脈の狭窄や閉塞 心臓の筋肉への血流が不足 胸痛を引き起こす | 安静や薬物療法 |
| 高血圧 | 血圧が高い状態が続く病気 脳卒中や心臓病のリスクを高める | 生活習慣の改善や薬物療法 |
さ行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 褥瘡 | 寝たきりやずり落ちなどにより、皮膚が圧迫され潰瘍ができる状態 | 早期発見と適切なケア |
| 心不全 | 心臓のポンプ機能が低下 体に十分な血液が送れなくなる 息切れやむくみなどを引き起こす | 薬物療法や生活習慣の改善 |
た行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 糖尿病 | 血糖値が高い状態が続く 合併症に注意 | 食事療法、運動療法、薬物療法など |
| 体温 | 体の温度 発熱や低体温に注意 | 37℃以上は発熱とみなされることが多い |
な行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 認知症 | 記憶力、思考力、判断力などの認知機能が低下する状態 | アルツハイマー型認知症が最も多い |
| 脳梗塞 | 脳の血管が詰まる 麻痺や言語障害などを引き起こす | 早期の治療が重要 |
| 脳出血 | 脳の血管が破れる 激しい頭痛や意識障害などを引き起こす | 緊急の治療が必要 |
は行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 肺炎 | 肺の炎症 高齢者では重症化しやすい | 早期の治療が重要 |
| パーキンソン病 | 震えや硬直、動作緩慢などを引き起こす神経変性疾患 | 進行性の病気で、現在のところ根本的な治療法はない |
| 頻脈 | 脈拍が速い状態 様々な原因が考えられる | 原因の特定が必要 |
| 便秘 | 便通が滞る状態 腹痛や膨満感を伴うことがある | 食事や水分摂取、運動などに注意が必要 |
ま行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 末梢循環障害 | 手足の先端部への血流が悪くなる状態 冷えや痺れなどを引き起こす | 糖尿病や高血圧などの合併症に注意 |
や行
| 用語 | 意味 | 備考 |
| 薬剤アレルギー | 特定の薬剤に対してアレルギー反応を起こす状態 | 薬剤の使用には十分な注意が必要 |
※上記は一般的な説明であり、個々の症状や治療法は異なる場合があります。
詳細な情報は医師や専門家にご確認ください。
まとめ

介護現場でよく見られる高齢者特有の疾患TOP10、感染症対策、医療的ケアが必要な病気とその対応、そして利用者との円滑なコミュニケーションについてご紹介しました。
比較的かかることが高い主要疾患(認知症、脳血管疾患、心臓病)、肺炎、骨粗鬆症だけでなく、
褥瘡、経管栄養、吸引といった医療的ケアも、
介護施設だけでなく在宅介護でも関わることが増えています。
介護者にとって、利用者の病状を理解し、適切なケアを提供することは非常に重要です。
そのためには、それぞれの病気の症状、原因、そして適切なケア方法について知識を持つことが不可欠です。
特に、初期症状や予兆を早期に発見することは病気の進行を遅らせ、利用者のQOL向上に大きく貢献します。
日々の観察を通して、少しでも異変を感じたらすぐに適切な対応を取るよう看護とも連携が大切です。
高齢者の健康状態は日々変化します。
予兆を見逃さないために、日々の観察と記録を丁寧に行い、疑問点があれば上司や医療関係者への相談を積極的に行いましょう。
継続的な学習とチームワークによって、より質の高い介護を提供することが可能になります。



