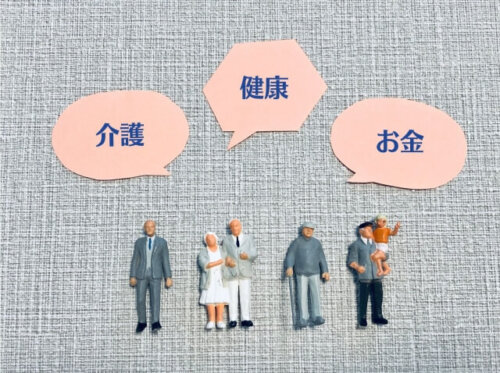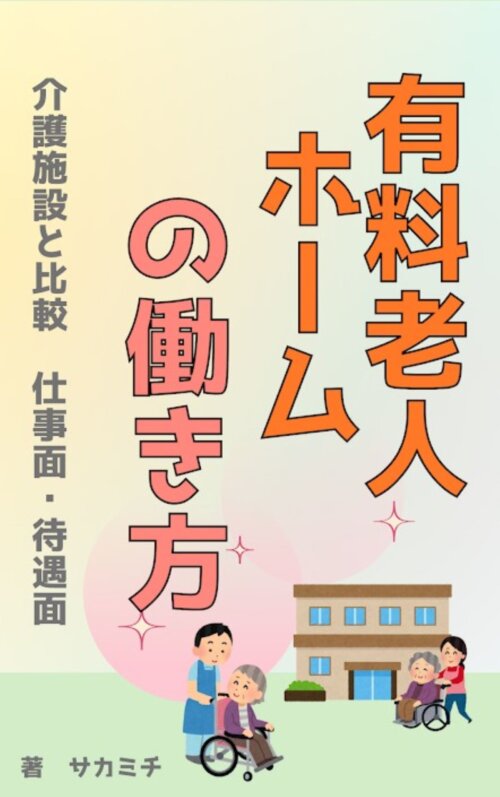高齢になると、
今までできていたことができなくなったり
老後の生活が不安になったり、悩みは尽きません。
今回は、そんな高齢者の困りごとをランキング形式でご紹介します。
あわせて、対処法や解決策もお伝えしますので
老後の生活に不安を感じている方はぜひ最後までご覧ください。
データで見る高齢者の悩み
高齢者の悩みは実に多様です。
厚生労働省などのデータでは、
- 健康不安に悩んでいる→70%以上
- 経済的な不安に悩んでいる→60%以上
- 孤独・孤立感に悩んでいる→50%以上
- 介護問題に悩んでいる→40%以上
どれも深刻で、悩みや困ったが高齢者の生活の質を低下させます。
経済的な問題や孤独・孤立などは、社会問題となるものも少なくありません。
加齢による身体機能の低下や疾病によるマヒなどで、家事を含めたさまざまなことが困難になってきます。
高齢者の困りごと1~5位
では、高齢者の困りごとはどんなものがあるのでしょうか。
ここでは、1~5位のランキングをご紹介します。
| 困りごとランキング1~5位 |
|---|
| 1.外出困難 |
| 2.家事の負担 |
| 3.健康不安 |
| 4.孤独感・コミュニケーション不足 |
| 5.デジタルデバイド(情報格差) |
1.外出困難
加齢が原因で外出がおっくうになる、というのもありますが
- 歩行困難
- 公共交通機関の不便さ
- 移動手段の不足
などの原因もあります。
外出困難の影響は、「脳の活性化が低下する」というリスクも懸念されます。
2.家事の負担
一言で「家事」といってもその数はとても多く、簡単なものではありません。
一般的には
- 料理
- 掃除
- 洗濯
といいますが、ひとつひとつの工程も多く、
身体の状態によってはそれらの家事を行うことがつらくなってきます。
それぞれの家事にかかる手間を細かく見ていくと、
できなくなる原因は一つではなくいくつかの要因が重なって起こります。
買い物に行けない(外出困難)から作れない、などのように。
車いすだからコンロに立てない、
ひざが痛いからしゃがむ掃除ができない、
洗濯機が洗っても服を干せない、
などといったこともあるでしょう。
3.健康不安
健康不安には3つの種類があるといいます。
- 身体的健康不安(病気の発症)
- 精神的健康不安(認知症)
- 将来への健康不安(健康状態の悪化で日常生活が送れない)
「どうなるか分からない」から不安になるのです。
持病の悪化や病気の発症となると、
病院への受診が増えたり、処方された薬の管理といった問題も考えられます。
医療機関へのアクセスは、外出困難とも関わってきます。
4.孤独感・コミュニケーション不足
高齢化社会において、高齢者の孤独・孤立は深刻な問題。
一人暮らしや孤独感を抱えている高齢者は、うつ病や認知症などの発症リスクを高めてしまいます。
社会とのつながりが少なくなってしまう、ということが一番の要因です。
5.デジタルデバイド(情報格差)
今やインターネット・スマートフォンの進化は目まぐるしく、デジタル技術の活用は不可欠な社会となっています。
しかし、高齢者の多くはデジタル機器の操作に不慣れで
デジタルデバイド(情報格差)
に苦しんでいます。
けれど、デジタル化が高齢者の生活を豊かにしていることも事実。
これからの将来は、デジタルデバイドの克服は必須となってきます。
困りごと1~5位の解決策
| 困りごとの解決策 |
|---|
| 1.外出困難/「運動の促進」と「交通手段の確保」 |
| 2.家事の負担/「便利器具」と「外部サービス」 |
| 3.健康不安/「定期的な健康診断」と「相談窓口」 |
| 4.孤独感/「広報誌」の活用 |
| 5.デジタルデバイド/「便利なサービス」として受け入れ「サポート体制」を充実 |
1.外出困難の解決策
加齢による身体機能の低下や身体の状態により外出が困難になると、脳の活動低下といったリスクが考えられます。
また、足腰に痛みがあるとよけい動かなくなり、身体機能はますます衰えていきます。
身体機能を低下させずに、現状維持を目標としてできるだけ体を動かしましょう。
もちろん、無理をせず痛みがでない範囲で。
杖やシルバーカーなどの福祉用具を活用して、安全に外出することもおすすめです。
外出時の移動には車が欠かせない、ということもあるでしょう。
とはいえ高齢者の運転はいささか不安もあり、
可能な限り家族や友人の送迎に頼りたいものです。
家族などの送迎が難しければ、
「タクシー」「送迎バス・コミュニティバス」を優先的に検討しましょう。
2.家事の負担の解決策
家事の負担を軽くするには、
「スマート家電(IoT家電)」の活用がおすすめ。
スマート家電(IoT家電)とは、インターネットに接続された家電のこと。
調理に便利な材料を入れるだけの時短家電。
人気のロボット掃除機、乾燥機能のついた洗濯機、など家事の負担を軽くする製品は多数実用化されています。
ただ、デメリットとして
- すべて買い替えられない
- 使い方が分からない
なども考えられます。
家電以外の家事負担を軽減する対策は「外部サービス」の活用。
できないことは、訪問介護サービスやお弁当などの宅配サービスで補いましょう。
3.健康不安の解決策
健康状態の悪化は、定期的な健康診断を受けることで予防できます。
可能であれば、「総合診療ができるかかりつけ医」を持っておくことをおすすめ。
受診する医療機関が複数になれば、同じ薬が処方される「重複服用」という問題もでてきます。
医療費の増加にもつながるため、「おくすり手帳」を利用し薬の重複を予防しましょう。
お住いの地域の保健センターや地域包括支援センターなどの「健康相談窓口」も活用し、
しっかりと健康管理を行うことが健康不安の軽減につながります。
4.孤独感・コミュニケーション不足の解決策
社会とのつながりや家族・他者交流を保つことが一番です。
地域や社会とのつながりを持つために、まずは情報を集めたいと思います。
そこで活用したいのは「お住まいの地域の広報誌」です。
参加できるイベントやさまざまな講座の情報が記載されています。
趣味のサークル活動が見つかれば、新たな友人関係が構築でき日常生活の活性化にもつながります。
遠方にお住いのご家族でも、離れた地域の広報誌をインターネットで見ることができます。
親御さんが住んでいる自治体の広報誌を確認して情報を伝えてあげることも可能。
一度、検索してみてください。
5.デジタルデバイド(情報格差)の解決策
デジタル機器は、スマートフォンだけではありません。
タブレットや家電、見守りカメラなどもそうです。
高齢者が悩む、製品や機器の操作に関しては
①このボタンを押す
といった具合に手順を書いたマニュアルを作ってあげるといいでしょう。
高齢化社会の進展に伴い、高齢者の生活を支えるテクノロジーの重要性は非常に高まっています。
また、さまざまなセンサーやデバイスを用いて
「高齢者の行動や健康状態を遠隔でモニタリングできる」ことは
- 緊急事態への迅速な対応
- 日々の健康管理の支援
にもつながります。
スマートフォンやパソコンの教室、講習会などサポート体制を充実させ、デジタル機器への不安を解消していきましょう。
高齢者の困りごと6~10位
続けて、6~10位の困りごとです。
| 困りごとランキング6~10位 |
|---|
| 6.金銭問題 |
| 7.認知症への不安 |
| 8.介護問題 |
| 9.生活環境 |
| 10.趣味やいきがい |
6.金銭問題
高齢者の収入源の多くは「年金」です。
年金生活の高齢者にとって、生活費のやりくりは大きな負担となっています。
あわせて、物価高や医療費の増加なども生活を直撃。
急な入院などの予期せぬ支出、相続問題や財産分与の悩みなども経済不安の一因です。
年金だけでは老後の生活を支えられないことが分かっている現在、生活費の不足や将来への不安に対してどう対処すればいいのでしょうか。
7.認知症への不安
加齢に伴い、記憶力や判断力の低下が不安になる高齢者は少なくありません。
認知面が衰えてきた、という自覚があったり同居家族の気づき、介護サービスの体制が整っている人はいいのですが、単身や老々介護の生活では認知症に気付くのが遅れる可能性もあります。
認知症の進行で大きな事故を起こすことも心配ですが、
「清潔が保てない」ことも大きな困りごとです。
- 排泄の失敗
- 食べこぼし
- 身体や持ち物の汚れに気付かない
など。
また、認知症にも種類があり
- アルツハイマー型認知症
- 血管性認知症
- レビー小体型認知症
が多いといわれています。
早期発見であれば認知症を遅らせることも可能な現代。
そのため、できるだけ早く医療機関に相談できる環境を作っておきましょう。
8.介護問題
高齢化が進むにつれ、介護が必要となる高齢者も増加しています。
介護をする側とされる側のどちらも高齢者(65歳以上)、という「老々介護」も他人事ではありません。
単身で生活している高齢者は「誰にも頼れない」という感情をもち、さらに不安は増していきます。
介護問題に対しては、介護サービスを受けることを前提に
- 制度
- 種類
- 利用に関する情報
を調べておくことをおすすめします。
介護問題では、費用がどのくらいかかるのかが分からず不安、という人もいます。
まずは、介護認定を受けて支援もしくは介護度がいくつになるかを確認しましょう。
介護度により給付される金額が分かるので、自己負担の割合に応じて月額いくら支払えばいいか、の目安がつけられると思います。
9.生活環境
加齢に伴い、身体機能は低下していきます。
そのため、住環境のバリアフリー化は不可欠、住宅改修が必要なケースも出てくるでしょう。
住宅改修には介護保険を利用することも可能ですが、いくつかの条件や手続きに時間がかかる、といったデメリットもあります。
地域によってはリフォームに関しての支援や補助制度がありますので、お住いの自治体に問い合わせてみるのもいいでしょう。
また、近年は自然災害や豪雨などの被害も深刻なので、普段からの備えやハザードマップ、避難経路や避難場所の確認もしっかりしておきましょう。
10.趣味やいきがい
高齢期において、趣味やいきがいを持つことはとても大切です。
趣味を通じて社会とつながることは
- 孤独感の解消
- 認知機能の維持
にもつながります。
長くつづく老後の時間を楽しく過ごせるかどうかは、いきがいややりがい、趣味があるかないかで大きく変わってきます。
ただ、趣味はあっても身体機能の低下やマヒが残ったりすることで、できなくなってしまうこともあります。
そうなったとき、在宅や一人暮らしの高齢者であれば一日がとても長く感じるでしょう。
高齢者の趣味やいきがいを支援する取り組みは重要な課題です。
困りごと6~10位の解決策
| 困りごとの解決策 |
|---|
| 6.金銭問題/「家計の見直し」と「公的支援制度の活用」 |
| 7.認知症への不安/「専門機関」に相談 |
| 8.介護問題/「プロに任せる・制度の活用」 |
| 9.生活環境/「バリアフリー化や住宅改修」 |
| 10.趣味やいきがい/「社会とのつながりを持つ」 |
6.金銭問題への解決策
多くの高齢者が、老後に金銭面の不安を抱えています。「年金だけでは暮らせない」と実感している高齢者は
- 貯金を崩す
- 節約
- パートやアルバイト
などの対策を行い生活しています。
働けるうちは働く、という人の中には「仕方なく働く」というより「やりがいやいきがいを持ちながら楽しんで働く」という人もたくさんいます。
老後でも働ける体があるのであれば、そんなふうに考えて仕事をし、収入を得るのもいいと思います。
節約に関しては、生命を脅かす方法(エアコンを使わない、極端な食費の削減、など)はおすすめできませんが、家計の見直しを行いましょう。
どうしても生活が苦しいときは、地域の包括支援センターや社会福祉協議会などの窓口に公的支援制度の活用が可能か相談しましょう。
7.認知症の不安への解決策
認知症の進行を遅らせる効果が期待できる最新の治療薬があります。
認知症初期、または軽度という条件があるため、認知症の早期発見が重要。
高価な薬にはなりますが、保険適用される薬なので1~3割の負担。
高額医療費制度も利用できるので、経済的な負担は軽減できると思います。
生活習慣病の予防も認知症の発症リスクを低下させるので、健康的な生活を意識することも大切。
脳トレなどを積極的に行い、認知機能の低下を予防することもおすすめです。
運動を欠かさない人より他の人と会話をする人の方が認知症になりにくい、というデータもあります。
同居でなくても、電話などで家族と会話する、地域交流に参加する、かかりつけ医を持つ、など人とのつながりを持ち、認知症の不安を感じたらすぐに専門機関に相談しましょう。
8.介護問題に対する解決策
高齢になれば、誰かの助けが必要になることも仕方ありません。
多少の助けには感謝して頼っていいと思いますが、介護が必要な状態にならないことが理想。
身体の衰えを感じてきたら、まずは介護認定を受けましょう。
要支援・要介護状態になったら、地域の相談窓口や支援センターでどんなサービスが利用できるか相談。
要介護度に応じた給付金の支給限度額を確認できれば、月額いくらの自己負担が必要になるかが分かり、介護にかかる費用も把握できます。
家族の介護をしている人も、できるだけ自分の時間を持つようにして介護負担を軽減しましょう。
9.生活環境に対する解決策
身体機能の低下や疾病によるマヒがあると、自宅でそのまま生活していくことに不安を感じるでしょう。
介護認定を受けていれば、「介護保険を利用した住宅の改修工事」が可能です。
いくつかの条件や手続きに時間がかかる、などのデメリットはありますが、生活環境の改善にはとても便利な制度です。
要介護者も介護者も安心して生活するためにも、自治体や地域包括支援センターへ相談してみましょう。
ICTやAIといったテクノロジーの進化も、生活環境の不安を軽減してくれるツール。
テクノロジーを取り入れた生活も検討するとより安心です。
10.趣味やいきがいへの解決策
健康的な生活を送るために、趣味やいきがいを持つことは重要です。
とはいえ、身体機能の低下によってできなくなるものもありますが、経験を活かしボランティアとして若い世代に教えるといった場所があれば、社会貢献ややりがいにつながります。
新たな趣味を探してみることもおすすめ。
ボランティア活動や趣味の発見などに役立つものが「地域の広報誌」です。
趣味や社会参加は他者とつながることができ、やりがいやいきがいを持つきっかけにもなります。
孤独感の解消の先にあるのは、笑顔の老後生活です。
電子書籍「シニア世代の悩みごと10」
今回の記事の内容をより詳しく、実体験や働いている施設の高齢者の話も盛り込んだ、読みごたえのある電子書籍を出版しました。
タイトルは「シニア世代の悩みごと10」。
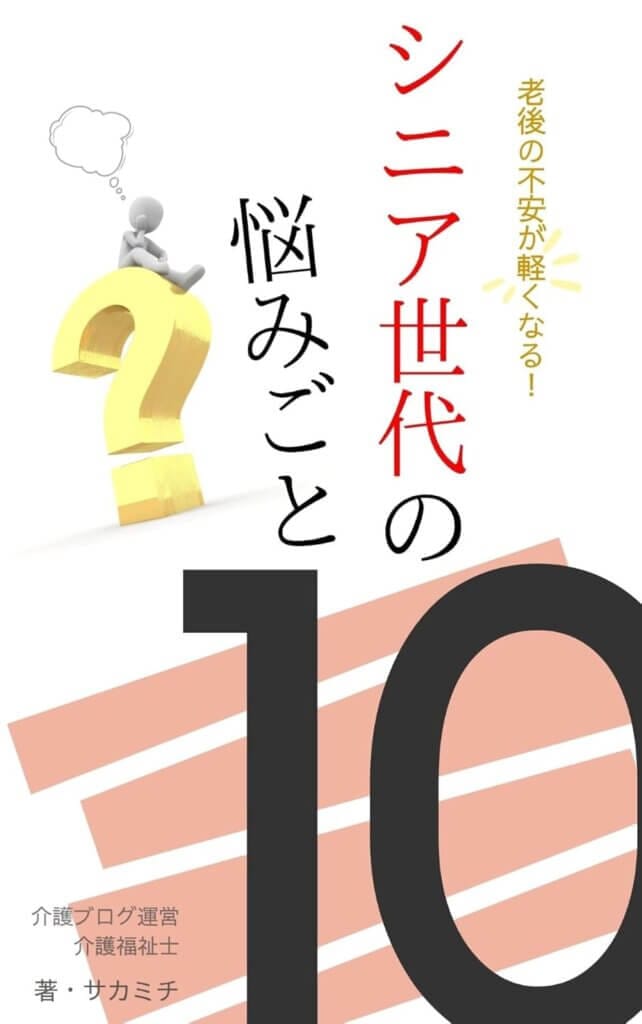
- 高齢者の生活を支えるテクノロジー
- 日常生活をサポートする便利グッズ
- 生活をより豊かにするサービス
- 社会問題の現状と解決策
- 多世代交流
などについても詳しくご紹介しています。
Amazonで450円で購入できます。
kindleアンリミテッドにご加入の方は無料で読むことができます。
ご興味がある方、もっと詳しく内容を読みたい方は、ぜひこちらからお願いします。
さいごに
高齢者やその家族が抱えている悩みは、それぞれ違って多岐にわたります。
私自身も実父と同居しており、今後さらに介護が必要になるのではないか、と不安に感じることもたくさんあります。
父の介護が終われば、私自身もすぐに高齢者となります。
今回の記事をきっかけに、自身の老後で悩みや困りごとがでてきても、どう対処すればいいかが分かり、不安は軽減されました。
電子書籍「シニア世代の悩みごと10」には書いていないことで、どうなるか分からない老後に私が備えていることをおまけでご紹介します。
とてもアナログだけどとりかかりやすい、
「エンディングノート」の活用。
「私について」のこと、好きな食べ物や好きなことも。
「苦手なこと・いやなこと」は、病院生活になったとき娘にお願いしておきたい。
「いろいろな手続きに必要な書類」「証明書」のこと。
「保管場所」、「交友関係」などなど。
あとに残された家族が少しでも助かるように、元気なうちから書きためておくといいですよ。
最近増えているのは、「デジタル遺品」という困りごと。
故人のスマホなどのパスワードやSNSのアカウントが分からなくて困る遺族が多いといいます。
一番重要なスマートフォンのIDやパスワードだけでも、家族で共有しておくと安心です。
エンディングノートを活用しながら少しずつ「終活」をすすめていると(あと数十年生きるとしても)、なんとなく老後の心配がひとつ減ったような気がしています。
子供や残された家族に迷惑をかけたくない、という気持ちは多くの人が持っている思いです。
「シニア世代の悩みごと10」にも、役立つ情報がたくさんあると思っていますが、読んでいただいた方で
「こんな対策をしています」
「こんなパターンのときはどうすればいい?」
「ちがう対処法を試しました」
などなど、コメントをたくさんいただけると今後の記事の参考になります!
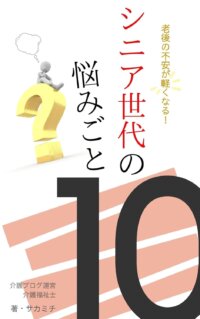
たくさんのご意見、お待ちしております。
こちらの記事も参考に。