高齢の親と同居していると

この先介護が必要になったらどうしよう、在宅で介護ができるだろうか?
いった不安を感じてしまう人は多いのではないでしょうか。
加齢とともに身体機能や認知機能、消化機能の低下などが起こります。
今は健康だと思っていてもどうなるかは全く分からないのが現実です。
今回の記事は、高齢の親に介護が必要になった時の在宅介護について悩みや課題、解決策を経験者の視点からお伝えします。
具体的な方法やテクニック、在宅介護の最新情報も合わせてご紹介しますので、どうぞ最後までお付き合い下さい。
在宅介護の悩み
- 介護状態になったとき、どのような症状になるか?(片麻痺や半身不随のような身体的なものか、認知症の症状か)
- 在宅介護を選択して仕事は続けられるのか?
- 私(介護者)が自分の時間を取れるのか?体は休められるのか?
- 父の介護保険や年金だけで賄えるのか?
- 私一人に介護の負担がかかるのではないか?
- 自立を促せるよう自宅の改修や住環境を整える必要はあるか?
同居での介護の場合、仕事をセーブしなくてはいけないのでは?と
私自身の収入が減ることと
介護にかかる費用、
介護を背負う精神的負担に悩みました。
介護を仕事として長年やっていますが、親を介護するとなるとやはり戸惑います。
私の場合、同性の母になら排泄や入浴介助ができても、父に対してだと実の親だからこそお互いやりにくい気持ちがでてしまいます。
在宅介護は喜びや楽しみがある反面、たくさんの課題があるのも現実です。
| メリット | 課題 |
| ・家族の絆を深める ・介護される側の尊厳を守る | ・介護する側の身体的・精神的・経済的負担が大きい ・介護される側の生活の質や社会との繋がりを維持することが難しい |
在宅介護は決して簡単ではありませんが、家族の絆や尊厳を守ることができる素晴らしい選択です。
介護する側・される側双方の負担を理解することが大切なんですね。
在宅介護経験者の視点
在宅介護は「身体的・精神的・経済的な負担に直面」します。
介護用品でおなじみの「フランスベット」が2021年に実施したアンケート
『在宅介護で大変なことランキング10選』
- 相手とのコミュニケーション
- 排泄の介助
- 精神面
- 時間面
- 食事の介助
- 入浴の介助
- 経済面
- 徘徊
- 身だしなみのケア
- 特にない
(フランスベット「在宅介護とは?在宅介護サービスの種類やメリット・デメリットをご紹介」から抜粋)
介護疲れや介護うつ、介護の時間を取るため社会問題にもなっている介護離職、介護する側が息子・娘(男性か女性か)によって変わるケアに対しての負担があります。
介護経験者でない人が介護を行う場合によく聞かれる言葉です。

食事や排泄などの介助は、どうやればいいのかが分からなくて腰痛になったり怒ったりしてしまいます

親の介護なので迷惑をかけないように自分でできる限りしなくては、と思っていますが、仕事をしながらできるものでしょうか?
仕事と介護の板挟みで疲弊してしまい、介護離職という結果になる人もいます。
在宅介護をしたい、という人の一番は
「親(介護される人)には住み慣れた場所で、安心して生活してもらいたい」という視点や気持ちだと思います。
ただ、離職をしてまで介護に専念してしまうのはストレス発散や気持ちのよりどころがなくなることもあり、あなた自身が犠牲になる可能性もあります。
それはできるなら避けたいことです。
「子供として私が介護できる部分はどれか」
「気持ちを尊重した上で親が受け入れてくれるのはどのサービスか」
「介護離職をせず、自分たちの生活ペースを大きく変えなくてすむ経済的支援はあるか」
と使えるサービスや制度を調べることがベストではないでしょうか。
在宅介護の課題と解決策
在宅介護には介護する側にもされる側にも課題や問題が発生します。
介護する側の負担
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 身体的な負担 | 腰痛 転倒事故 疲労の蓄積 |
| 精神的な負担 | ストレスの高まり 介護うつ 孤独感 |
| 経済的な負担 | 仕事をセーブした場合、収入減 介護サービスの利用費用 福祉用具の購入費用 |
介護される側の負担
| 課題 |
|---|
| 生活の質の低下 尊厳を傷つけられる恐れ 社会との繋がりを維持することの難しさ |
在宅介護は介護する側の負担が大きく取り上げられますが、介護される側にも負担が強いられます。
身体的な介護ニーズと精神的なケアです。
お互いの立場を理解し負担を少しでも軽減する方法を話し合っておきたいですね。
解決策
これらの課題や問題の解決策としては、主に介護保険制度を上手く活用すること。
介護保険サービスは「要介護・要支援」の認定を受けた人だけが利用でき、認定を受けると1~3割の自己負担で利用できます。
まずは介護認定の申請を行うことから始めましょう。
在宅介護の具体的な方法やテクニック
在宅介護において、日常生活の大部分を占める介助は食事・入浴・排泄です。
ある程度の技術が必要となる介助で、安全性と尊厳の確保が何よりも重要となります。
【介助別】コツ・サポート方法
| 食事介助 | 入浴介助 | 排泄介助 |
| ・栄養摂取を心がける ・楽しい時間になる工夫をする ・嗜好や状態に合わせた食事形態 ・一緒に会話を楽しむ | ・身体機能の状態によるが一般的な浴槽の使用をおすすめ ・転倒リスク対策として福祉用具の使用 | ・プライバシーへの配慮が不可欠 ・尊厳を傷つけやすい行為 ・気持ちを汲み取る ・声かけや目線の調整 |
〈食事のサポート〉
| 注意点 | 対策・ポイント |
|---|---|
| 誤嚥を防ぐ | ・あごがあがらないように注意(食べさせるときは目線を合わせる) ・クッションで頭を固定するなど工夫してあごをひく ・飲み込んだタイミングで適宜声掛けをする |
食べさせ方は分かっても、栄養バランスを常に考えて食事を作るのは大変です。
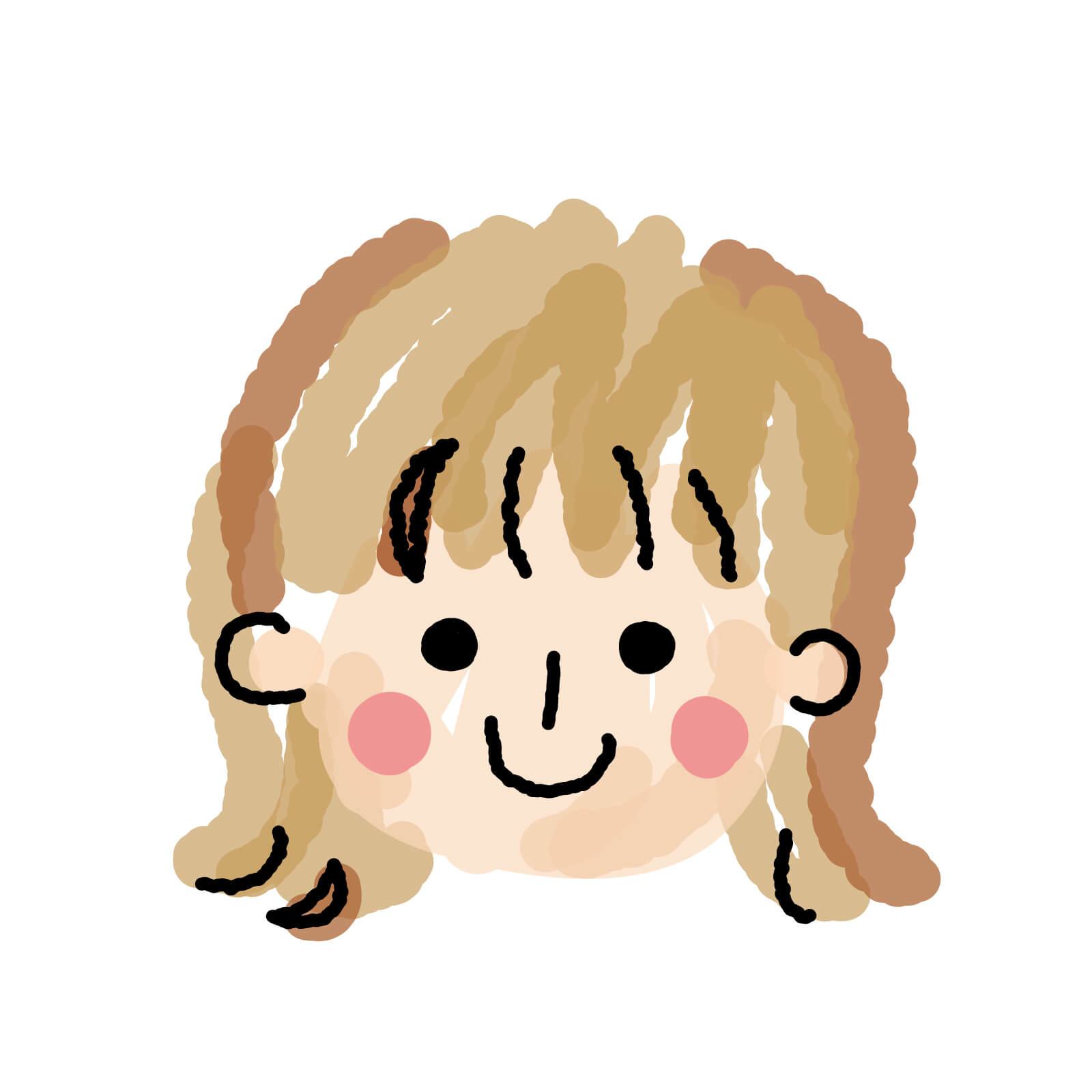
仕事もしているので料理ができるのは休みの日くらいだと思っています。
毎日の食事の献立を考える負担をなくすため、
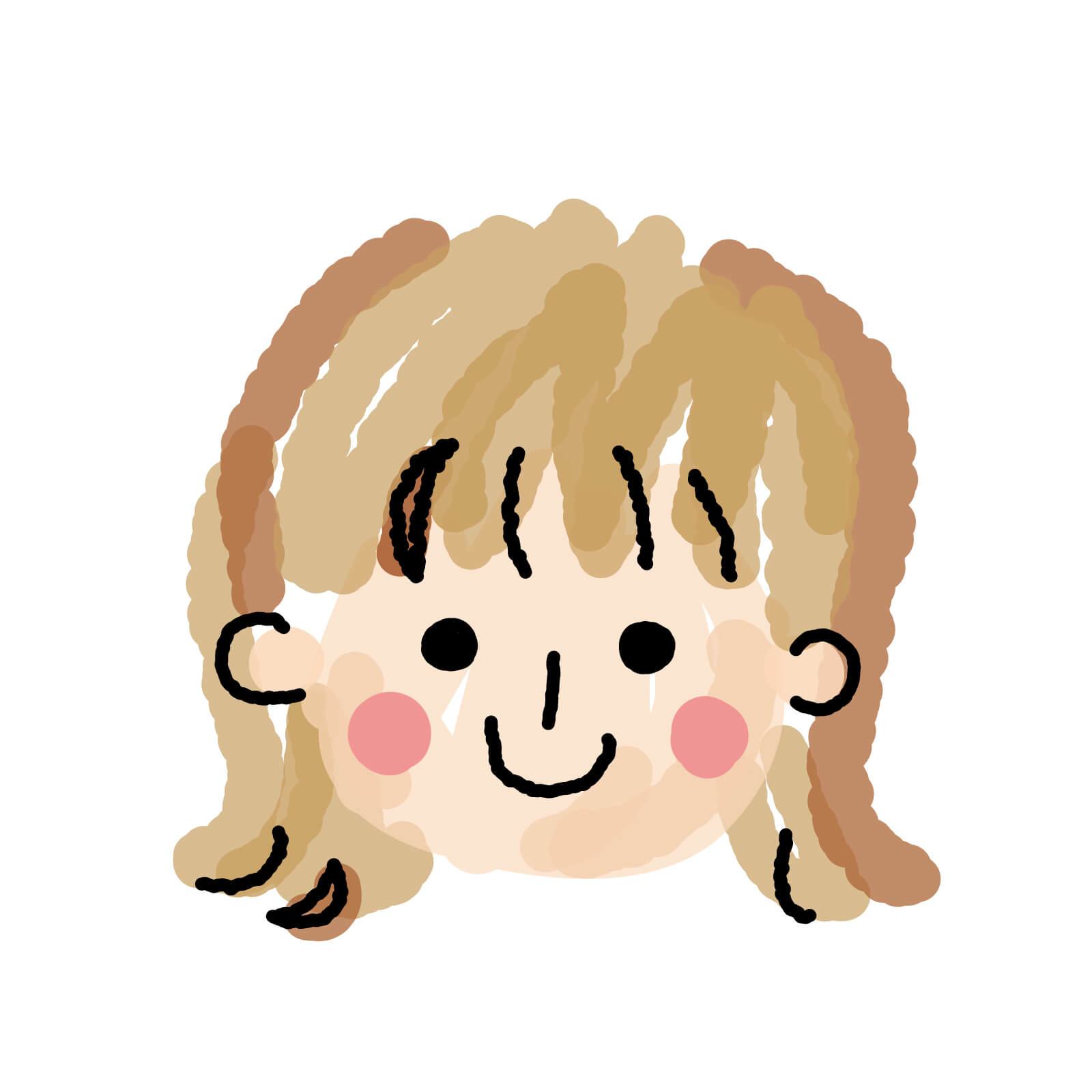
迷わず、介護食の宅配お弁当を利用するつもりです!
その方が、たまに作る平凡な私の料理が新鮮に感じるかもしれません♪
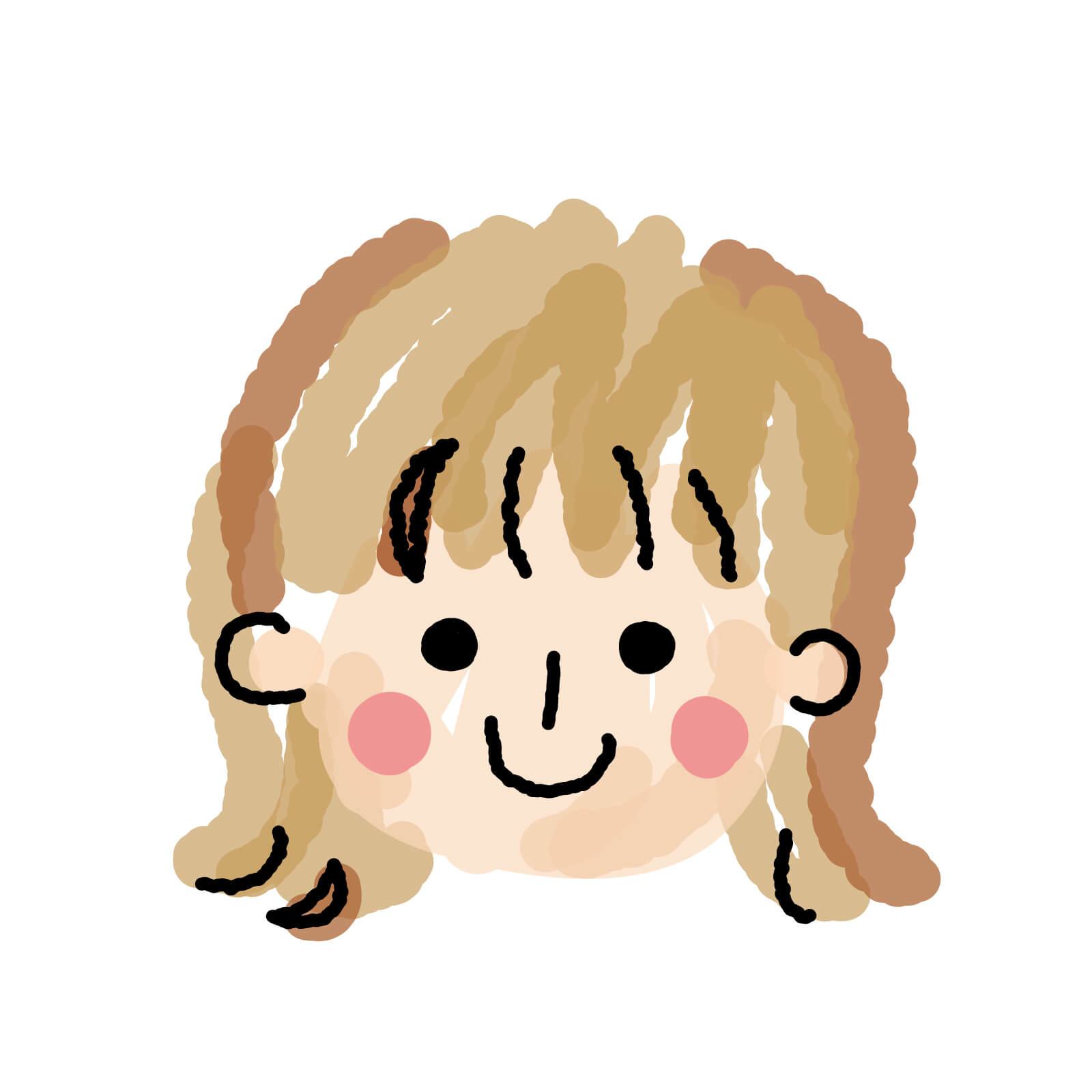
今の宅配食は、一昔前のお弁当と比べると種類も豊富だし、味付けもかなり美味しくなってます!
おすすめの宅配お弁当です。
また、嚥下機能が低下している要介護者の場合、誤嚥に気をつけることが重要です。こちらの記事も参考に。
食事介助は安全を最優先で行います。
〈入浴のサポート〉
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 環境面での対策 | 滑り止めマットや手すりの設置 |
| 動作時の対策 | 転倒防止の声かけを行う(手をつく位置など動作の誘導) お湯は適温か確認 |
| 全体 | 安全面に十分気を付けながら気持ちよく(リラックスして)入浴できるようにする 事故が起こりやすい場所だという認識を持つ 入浴前にバイタルを図る 入浴後は水分補給や保湿クリームなどをすすめる |
浴室、脱衣室には福祉用具の設置を必ず行う。
〈排泄のサポート〉
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 環境面での工夫 | ポータブルトイレを置くときは仕切りを設置(見えないように配慮) 手すりの設置(自立を促し介助の負担を軽減) 排泄のサイクルを把握する |
| 介助時のコミュニケーション | 大きな声で声かけしない(周囲に排泄していると伝わらないように) 陰部の露出時間を最小限に抑える(プライバシーを守る) 尿や便の色や状態など話しやすい関係にして健康状態を確認 ズボンの上げ下ろしや動作を過剰に介助しすぎない |
排泄でミスをして汚したとしても、責めたり怒ったりしないことが大切です。
在宅介護で実践できるケア
良好な関係を築くためには介護コミュニケーションが重要となります。
介護する側はスキルアップになり、介護される側は安心して任せられる。
コミュニケーションはケアの質を上げるために不可欠です。
言葉だけでなく、表情やしぐさといった非言語的なコミュニケーションも欠かせません。
良好な関係を築くためのポイントは2点。
- 傾聴の姿勢|相手の気持ちを理解し受け入れる姿勢
- ポジティブな言葉かけ|利用者の尊厳を傷つけないよう肯定的な言葉遣いを心がける
傾聴の姿勢|相手の気持ちを理解する
- アイコンタクトで相手に集中していることを体全体で示す
- 相手のペースに合わせて話を聞き、相槌を打つなどして共感を示す
- 表情を豊かに変え、言葉以外の非言語コミュニケーションにも気を配る
相手の気持ちに共感することで信頼関係を築くことができます。
介護される方の尊厳を守り、より良い介護に繋げたいですね。
ポジティブな言葉かけ|自尊心を傷つけない
- 「できないところは手伝うよ」と自分でできる行為は尊重した言葉かけ
- 「頑張っているね」「お疲れさま!」と肯定的な言葉をかける(自信や意欲を高める)
- 「一緒に頑張ろうね!」と共感的な言葉をかける(孤独感を和らげ前向きになる)
相手の自立心を尊重することで、介護する側は介助の負担が軽減でき、介護される側は身体機能の低下防止になります。
在宅介護を支える制度|知って得するサービス&利用方法
在宅介護を支えるには介護保険制度の活用が欠かせません。
認定の結果に基づき介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する ケアプランに沿って、様々なサービスを利用できます。
主なサービスとしては、
- 訪問介護(ホームヘルパーの派遣)
- 訪問入浴
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所)
などがあります。
費用の一部は介護保険から給付され自己負担は1~3割で利用できます。
地域包括支援センター|相談窓口を有効活用しよう
在宅介護では様々な不安や疑問が生じますが、そんな時に頼れるのが「地域包括支援センター」です。
地域包括支援センターは介護に関する総合相談窓口として、以下のようなサポートを行っています。
- 介護予防への助言
- 介護サービスの利用に関する相談対応
- 高齢者の権利擁護
- 介護者への支援
センター内には保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門スタッフが在籍しており、チームで高齢者の生活を多角的にサポートしてくれます。
全国に約6,700カ所の拠点があり気軽に相談できる身近な存在です。
在宅介護で不安なことがあればひとりで抱え込まず、地域包括支援センターを有効活用しましょう。
厚生労働省「地域包括ケアシステム」からお住いのセンターを探してみて下さい。
最新トピック
最近は認知症の人も在宅介護をしなければいけない状況も多くなり、
「在宅介護における認知症ケア」
「認知症の症状に合わせた対応」などの情報も増えています。
認知症の代表的な症状は「徘徊」と「妄想・幻覚」
〈徘徊への対応〉
認知症の症状の一つである「徘徊」は、高齢者が目的もなくうろうろと歩き回る行為を指します。
外に出てしまい行方不明になったり、交通事故に巻き込まれるリスクもあります。
しかし、徘徊には何らかの理由があることが多いため怒るのではなく、冷静な対処が求められます。
有効な対策として
- GPSグッズの活用:現在地を把握できるため安全確保に役立つ
- 外出の機会を設ける:散歩やドライブなどの外出を取り入れることで適度な疲労感と徘徊への欲求を満たす
- 外出時は名前と連絡先を記入した物品を所持させる
- 生活リズムを整える:規則正しい生活は不安感が和らぎ徘徊が減る可能性がある
- センサーなどを活用し外出を検知
- 鍵の管理を徹底し外出を防ぐ
〈妄想・幻覚への対応〉
認知症の症状である妄想や幻覚は、介護する側からすると現実とかけ離れていることがあります。
けれど否定したり無理に現実を押し付けるのではなく、傾聴し気持ちに共感することが大切です。
- 否定せず受け入れる
- 気分転換を図り注意をそらす
- 本人の気持ちに共感する
穏やかな対応が求められます。
幻覚の内容を確認し危険性がなければ、その体験を尊重し寄り添う対応をしてみましょう。
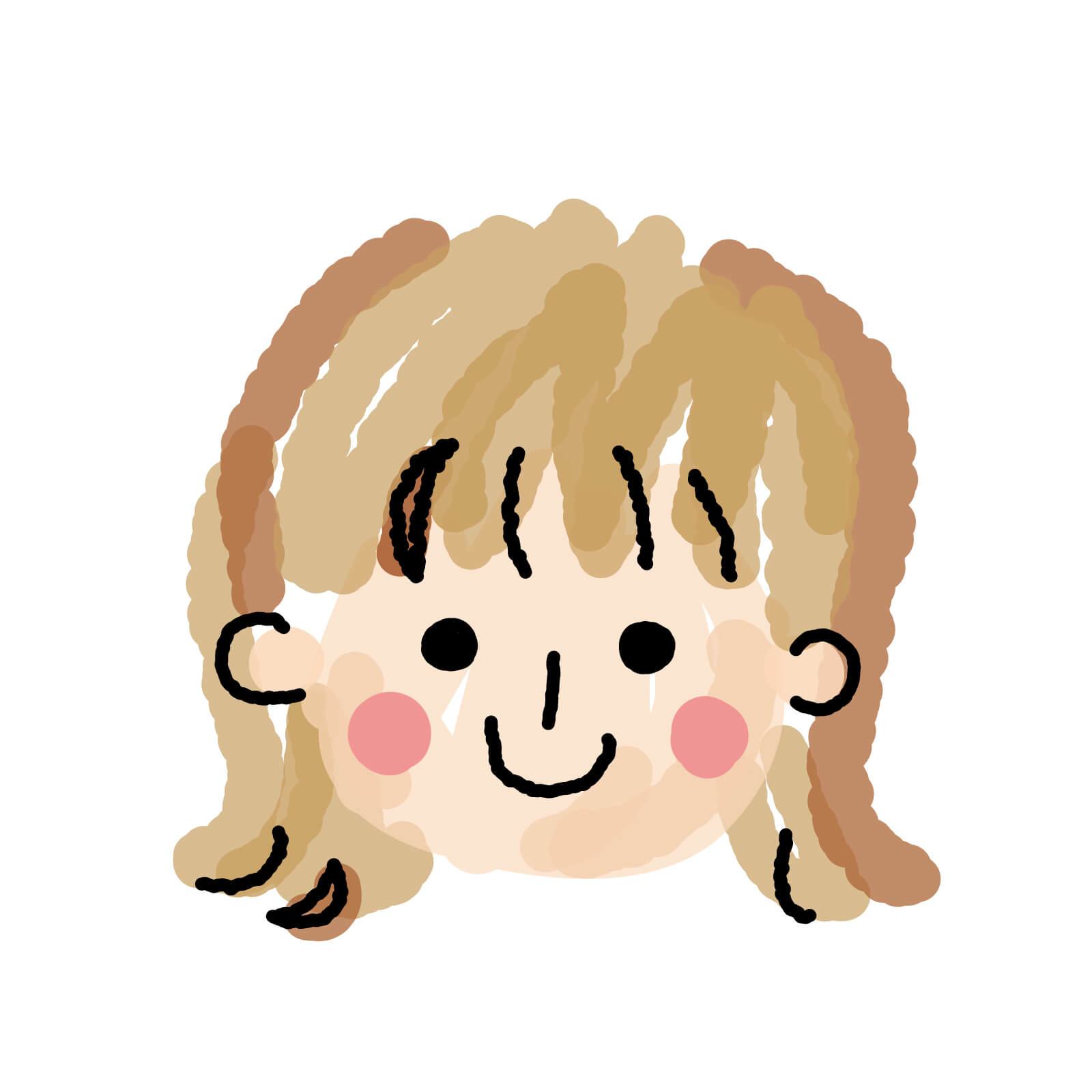
私は最近、「見守りカメラ」を設置しました。
スマホからも確認できますし、今後介護が必要になれば設置してよかったと思うでしょう!
設置した見守りカメラは、「日本在宅介護協会認定商品」!
MANOMA(マノマ)「親の見守りセット」詐欺対策
認知症の高齢者がひとりで留守番をするとき、
「何かの事件に巻き込まれないか」ということも心配のひとつです。
- 電話や玄関のドアに「出ない」という紙を貼っておく
- 電話に「迷惑防止機能」がついたものにする
などの対策もおすすめです。
我が家も詐欺対策、防犯対策でカメラを設置しました。
こちらの記事も参考に。
介護負担を軽減する便利グッズ|おすすめアイテム
便利グッズといえば『福祉用具』『介護用品』です。
福祉用具や介護用品は日々進化を遂げており、在宅介護の強い味方と言えるでしょう。
介護用ベッド
体位変換や移動がスムーズにできるタイプ、電動リモコン操作で高さ調節が可能なものなど多くの機能を備えた介護用ベッドは、介護者の腰痛リスクを軽減します。
- 背上げ機能:利用者が自力で上体を起こせるよう支援
- 高さ調節機能:介護者の腰への負担を軽減
- 膝上げ機能:寝返りや移乗時の動作をサポート
入浴補助具
浴槽台・回転チェア・滑り止めマットなどなど、入浴補助具は種類も多く自宅の浴室に合ったものを探せば安全に入浴できます。
- 浴槽内椅子: 浴槽内に設置し、座った状態で入浴できる
- 浴槽台: 浴槽の縁に設置し、腰掛けて入浴できる
- 滑り止めマット: 浴槽内の滑りを防ぐ
- 浴槽手すり:安全に浴槽へ出入りできる
介護される側の状態に合わせて選ぶ必要があるので福祉用具専門員やケアマネジャーに相談するといいでしょう。
その他、排泄用品や移動支援用品など様々な介護グッズが充実しています。
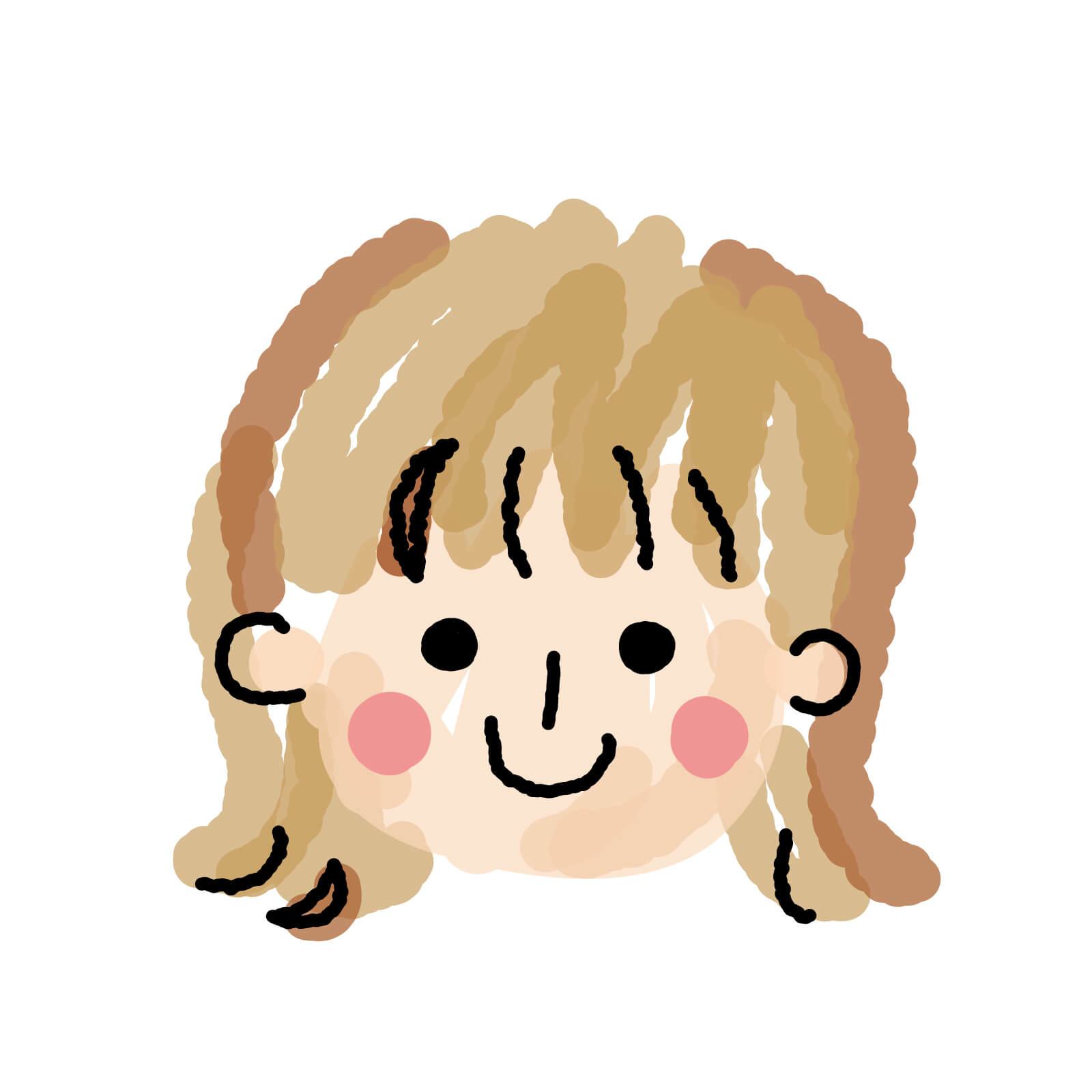
インターネットで「介護用品」を検索すると、人気商品の最新トレンドがチェックでき楽しいですよ
介護の負担も軽減できお互いにとってよい在宅介護生活が送れます。
介護負担からは少し外れますが、
聞こえにくくなった高齢者に最新アイテムを使えばコミュニケーションも取りやすくなります。
ご紹介している記事も参考にして下さい。
まとめ
在宅介護は介護する家族にとって身体的・精神的・経済的に大きな負担となります。
介助技術が分からなかったり、時間と体力の限界、費用の負担増など乗り越えなければならない壁はたくさんあります。
一方で、介護される側も生活の質の低下や尊厳を傷つけられるリスク、社会との繋がりを失うことへの不安があります。
お互いの立場を理解して、少しでも負担が軽くなるような在宅介護にしていきたいと思います。
在宅介護は家族の絆を深める喜びを感じることができます。
しかし、介護の現実、予期せぬ出来事や困難に直面することもあると感じています。
例えば、
- 体力を要する排泄や入浴の介助
- 日常の家事負担の増加
- 収入面の不安
- 精神的な負担
- 体調の変化
- 身体機能の低下や認知症の症状
などです。
さまざまな支援サービスは上手に活用することが重要です。
ただ、個人的には在宅介護で限界を感じたときは施設や有料老人ホームへの入所も検討すべきだと感じています。
在宅介護経験者のリアルな声、ホーム入居を選択した理由やメリットなども照らし合わせて自分たち家族はどのケースが最適か話し合うことも大切ですね。
老人ホームなどの検索は専門のサイトがおすすめ!
老人ホーム検索サイト みんなの介護







